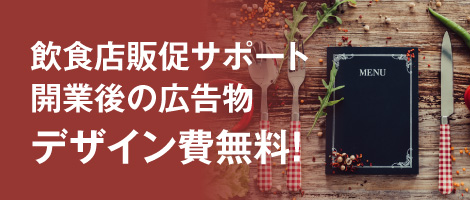- トップ
- 飲食店の多店舗化を実現する効き脳とは(後編)~チームビルディングとダイバーシティ経営
飲食店の多店舗化を実現する効き脳とは(後編)~チームビルディングとダイバーシティ経営
脳科学からの効き脳
愛知県の「オモロイ」飲食店の創業や多店舗化を
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。
前々回、前回に引き続き、
今回も「効き脳」について説明します。
前々回のコラムでは、
脳の効き(強みと弱み)についてザックリと、
前回のコラムでは、
主に強みについて書いてきました。
「効き脳」についての脳科学的な説明は、
専門的すぎると思い避けてきたのですが、
想像以上に
「右脳」と「左脳」に興味がある方もいるらしいので、
ハーマンモデル/効き脳について脳科学的にご紹介します。
1.右脳・左脳モデル
1981年にノーベル賞を受賞した、
ロジャー・スペリーらの研究により、
脳には、
論理的、分析的に働く左脳と、
直感的・全体的に働く右脳
の2つの異なる機能があることが明らかにされました。
2.三位一体型脳モデル
ポール・マクリーンが提唱した学説。
人間の脳は
「脳幹」「辺縁系」「大脳新皮質」
の順に発達し、
それら3つの機能を持つ脳が一体となって働くという理論。
思考に関する部分は、
「大脳新皮質」(脳の上層部)と
「辺縁系」(大脳新皮質の内側)であるとされます。
因みに
外側の大脳新皮質は「霊長類の脳」
内側の辺縁系は「哺乳類の脳」
と分類しています。
3.ハーマンモデル/効き脳
GE社(ゼネラル・エレクトリック)の社員教育の責任者、
ネッド・ハーマン氏によって構築された理論。
「右脳・左脳モデル」と「三位一体型脳モデル」を統合したもの。
人間の脳は、「右脳」・「左脳」それぞれで、
「大脳新皮質」と「辺縁系」が
異なる働き方をしていると考えた。
そして、
「左脳」の「大脳新皮質」の働きを、A(論理・理性脳)
「左脳」の「辺縁系」の働きをB(堅実・計画脳)
「右脳」の「辺縁系」の働きをC(感覚・友好脳)
「右脳」の「大脳新皮質」の働きをD(冒険・創造脳)
と「思考特性」(脳の強み・弱み)を分類し、数値化しました。
つまり、ハーマンモデル理論は、
個々の思考特性を数値化・可視化して、
それまで漠然としていた
個人の思考特性と様々な言動との関連性を定義づけたものです。
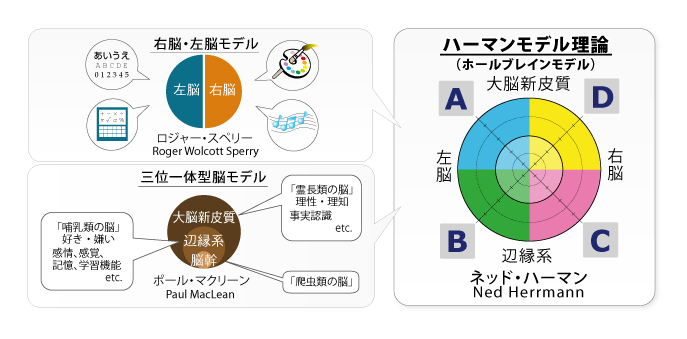
出典:フォルティナ株式会社
効き脳の指数の合計は200点と一定で、
その200点をを各分野に数値化したものが
人の強み・弱みを表していますが、
あくまで一人ひとりの思考特性を数値化したものであり、
優劣や良し・悪しを示すものではありません。
人間の血液型に優劣がないのと
同じことだととらえてください。
「お金」と「チームビルディング」で
戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。
前々回、前回に引き続き、
今回も「効き脳」について説明します。
前々回のコラムでは、
脳の効き(強みと弱み)についてザックリと、
前回のコラムでは、
主に強みについて書いてきました。
「効き脳」についての脳科学的な説明は、
専門的すぎると思い避けてきたのですが、
想像以上に
「右脳」と「左脳」に興味がある方もいるらしいので、
ハーマンモデル/効き脳について脳科学的にご紹介します。
1.右脳・左脳モデル
1981年にノーベル賞を受賞した、
ロジャー・スペリーらの研究により、
脳には、
論理的、分析的に働く左脳と、
直感的・全体的に働く右脳
の2つの異なる機能があることが明らかにされました。
2.三位一体型脳モデル
ポール・マクリーンが提唱した学説。
人間の脳は
「脳幹」「辺縁系」「大脳新皮質」
の順に発達し、
それら3つの機能を持つ脳が一体となって働くという理論。
思考に関する部分は、
「大脳新皮質」(脳の上層部)と
「辺縁系」(大脳新皮質の内側)であるとされます。
因みに
外側の大脳新皮質は「霊長類の脳」
内側の辺縁系は「哺乳類の脳」
と分類しています。
3.ハーマンモデル/効き脳
GE社(ゼネラル・エレクトリック)の社員教育の責任者、
ネッド・ハーマン氏によって構築された理論。
「右脳・左脳モデル」と「三位一体型脳モデル」を統合したもの。
人間の脳は、「右脳」・「左脳」それぞれで、
「大脳新皮質」と「辺縁系」が
異なる働き方をしていると考えた。
そして、
「左脳」の「大脳新皮質」の働きを、A(論理・理性脳)
「左脳」の「辺縁系」の働きをB(堅実・計画脳)
「右脳」の「辺縁系」の働きをC(感覚・友好脳)
「右脳」の「大脳新皮質」の働きをD(冒険・創造脳)
と「思考特性」(脳の強み・弱み)を分類し、数値化しました。
つまり、ハーマンモデル理論は、
個々の思考特性を数値化・可視化して、
それまで漠然としていた
個人の思考特性と様々な言動との関連性を定義づけたものです。
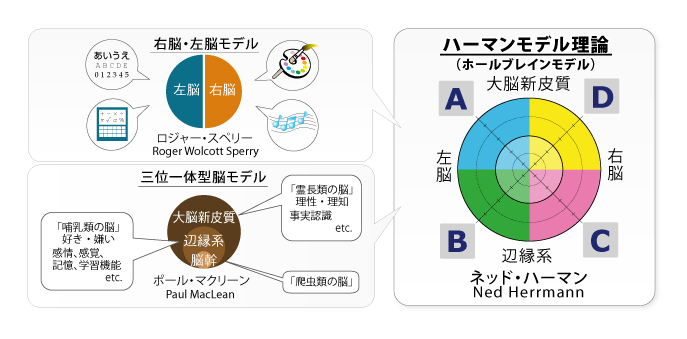
出典:フォルティナ株式会社
効き脳の指数の合計は200点と一定で、
その200点をを各分野に数値化したものが
人の強み・弱みを表していますが、
あくまで一人ひとりの思考特性を数値化したものであり、
優劣や良し・悪しを示すものではありません。
人間の血液型に優劣がないのと
同じことだととらえてください。
ダイバーシティとチームビルディング
最近、新聞紙面などで、
ダイバーシティ
という言葉をよく目にします。
もともとは、
アメリカにおいてマイノリティーや女性の
積極的な採用や差別ない処遇の実現
を謳って広まった考え方で、
私もそのように思っていました。
しかし、
ダイバーシティを直訳すると、
「多様性」
「幅広く性質の異なるものが存在すること」
という意味であるそうです。
そして、経済産業省によると、
ダイバーシティ経営とは、
性別・人種・年齢・性格・価値観などの多様な違いを受入れ、
個々の能力を最大限引き出すことにより
付加価値を生み出し続ける企業を目指して、
全社的かつ継続的に進めていく取組
をいうそうです。
ここでいう、「能力」とは、
潜在的な能力や特性を含むそうです。
でも、
「違い」や「潜在的な能力・特性」が分からなければ、
それを引き出すことはできないですよね!?
そうです。
そこで活用できるのが、
思考特性を数値化・可視化した効き脳です。

己の強み・弱みを把握し、
仲間の強み・弱みを理解したうえで、
個人個人の強みを活かし、
弱みは補い合いながら、
飲食店の多店舗化のような高い成果を上げ、
かつ、成長を続ける組織づくり。
これが、チームビルディングです!
チームビルディングとダイバーシティって近いですね!
(根柢に流れる問題意識は同じなのでしょう)
ただいまHP開設記念として、
飲食店の多店舗化にチームビルディングを導入する場合に限り、
コンサルティングを半額で提供する、
半額モニターキャンペーンを行っています。
半額モニターキャンぺーはこちら
無料相談も受け付けていますので、
「ご相談・お問合せ」よりお問合せ下さい。
ダイバーシティ
という言葉をよく目にします。
もともとは、
アメリカにおいてマイノリティーや女性の
積極的な採用や差別ない処遇の実現
を謳って広まった考え方で、
私もそのように思っていました。
しかし、
ダイバーシティを直訳すると、
「多様性」
「幅広く性質の異なるものが存在すること」
という意味であるそうです。
そして、経済産業省によると、
ダイバーシティ経営とは、
性別・人種・年齢・性格・価値観などの多様な違いを受入れ、
個々の能力を最大限引き出すことにより
付加価値を生み出し続ける企業を目指して、
全社的かつ継続的に進めていく取組
をいうそうです。
ここでいう、「能力」とは、
潜在的な能力や特性を含むそうです。
でも、
「違い」や「潜在的な能力・特性」が分からなければ、
それを引き出すことはできないですよね!?
そうです。
そこで活用できるのが、
思考特性を数値化・可視化した効き脳です。

己の強み・弱みを把握し、
仲間の強み・弱みを理解したうえで、
個人個人の強みを活かし、
弱みは補い合いながら、
飲食店の多店舗化のような高い成果を上げ、
かつ、成長を続ける組織づくり。
これが、チームビルディングです!
チームビルディングとダイバーシティって近いですね!
(根柢に流れる問題意識は同じなのでしょう)
ただいまHP開設記念として、
飲食店の多店舗化にチームビルディングを導入する場合に限り、
コンサルティングを半額で提供する、
半額モニターキャンペーンを行っています。
半額モニターキャンぺーはこちら
無料相談も受け付けていますので、
「ご相談・お問合せ」よりお問合せ下さい。
飲食店開業なら
あいち飲食店開業支援
センターへ
最新情報 一覧
-
セミナー中小機構からの依頼で「あなたの強みを活かす方法」について、研...
2020.09.30
-
セミナー飲食店の働き方改革セミナー。働き方改革は飲食店の生き残りに必...
2020.05.31
-
経営改善新型コロナの影響で経営難に陥った飲食店への資金繰り支援策
2020.05.07
-
経営改善売上が激減している飲食店は、雇用調整助成金を活用し雇用を守り...
2020.03.22